扶桑会について
指導者: 石塚嘉 【達人・名人・秘伝の師範たち】
稽古日時:日曜14時半~16時半 / 木曜19時~21時
稽古場所:神道扶桑教 世田谷太祠 東京都世田谷区松原1丁目7−20 【道場紹介】
入会希望者が参加可能な公開稽古は4月29日(月・祝)13時30分から16時30分まで開催します。
場所は 世田谷区総合運動場 体育館 第一武道場です。
扶桑会への入会を希望される方は 左のメールフォームよりお問い合わせください。
扶桑会のYouTubeチャンネルでは「メンバー限定動画」の配信を始めました。一般公開の動画ではカットしている口伝や、道場でしか見せないコツを取り上げています。
興味のある方は 「Aiki-Kobujutsu」チャンネルホームページ にアクセスして「メンバーになる」から購読手続きしてください!
【扶桑会がTV放送されました!】
NHKWorld「J-arena」(↑上の画像をクリックすると無料視聴できます)
【関連商品】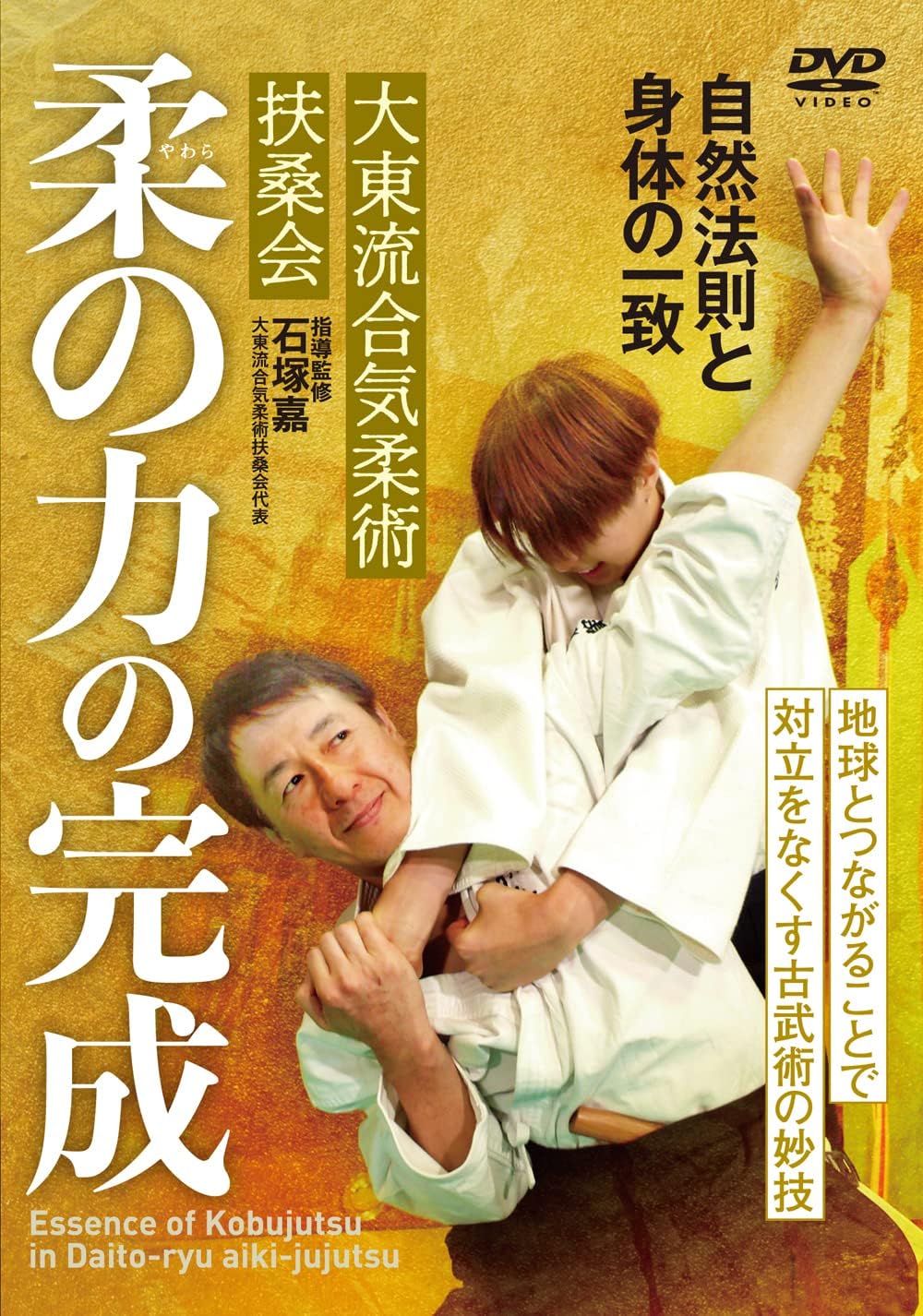 扶桑会DVD「柔(やわら)の力の完成」←Amazonへリンク
扶桑会DVD「柔(やわら)の力の完成」←Amazonへリンク
【Twitter】https://twitter.com/aiki_fusoukai
【Instagram】https://www.instagram.com/aiki_kobujutsu/
【Facebook】https://fb.com/kobujutsu
稽古日時:日曜14時半~16時半 / 木曜19時~21時
稽古場所:神道扶桑教 世田谷太祠 東京都世田谷区松原1丁目7−20 【道場紹介】
入会希望者が参加可能な公開稽古は4月29日(月・祝)13時30分から16時30分まで開催します。
場所は 世田谷区総合運動場 体育館 第一武道場です。
扶桑会への入会を希望される方は 左のメールフォームよりお問い合わせください。
扶桑会のYouTubeチャンネルでは「メンバー限定動画」の配信を始めました。一般公開の動画ではカットしている口伝や、道場でしか見せないコツを取り上げています。
興味のある方は 「Aiki-Kobujutsu」チャンネルホームページ にアクセスして「メンバーになる」から購読手続きしてください!
【扶桑会がTV放送されました!】

NHKWorld「J-arena」(↑上の画像をクリックすると無料視聴できます)
【関連商品】
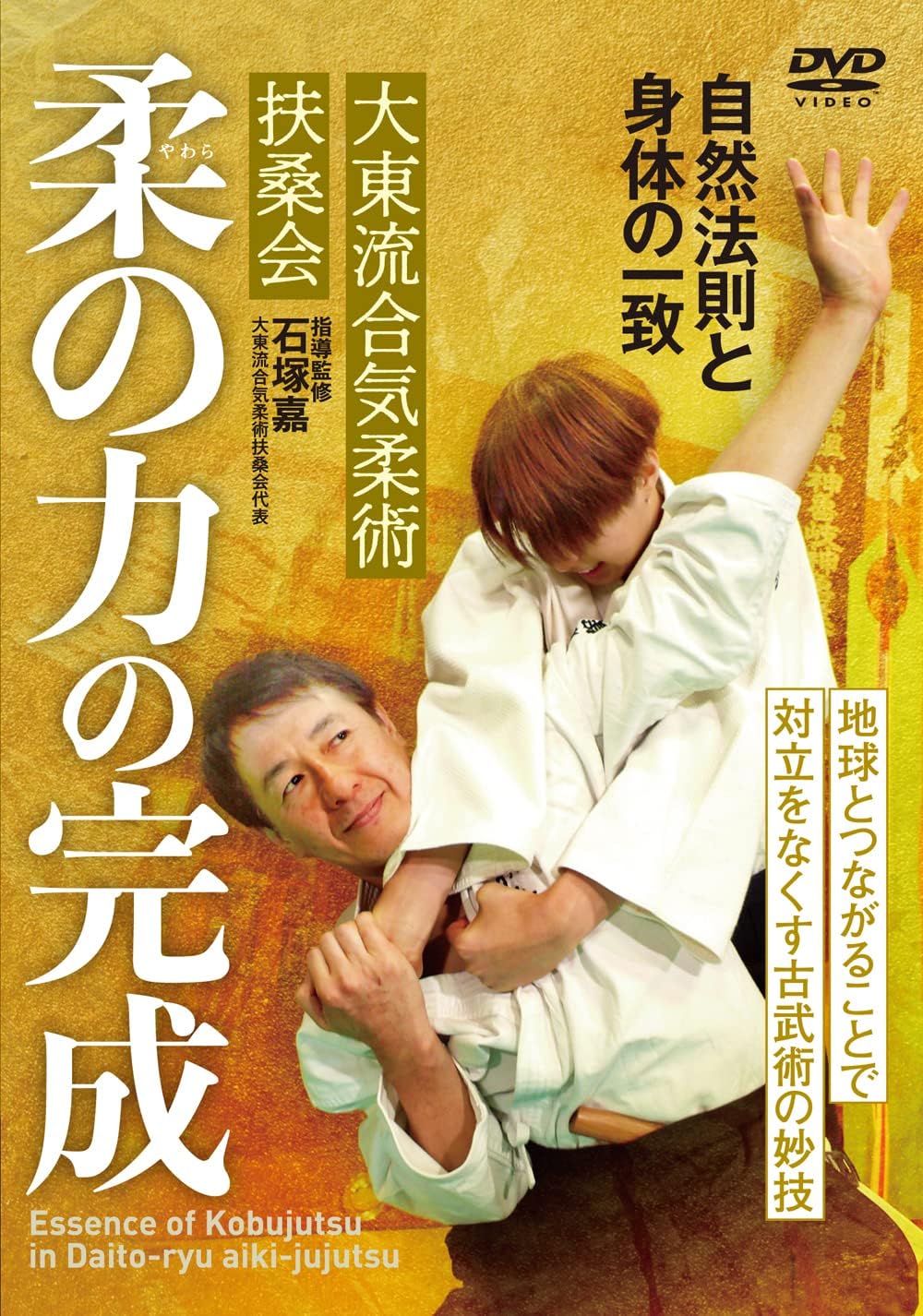 扶桑会DVD「柔(やわら)の力の完成」←Amazonへリンク
扶桑会DVD「柔(やわら)の力の完成」←Amazonへリンク
【Twitter】https://twitter.com/aiki_fusoukai
【Instagram】https://www.instagram.com/aiki_kobujutsu/
【Facebook】https://fb.com/kobujutsu
其の百四十四、中心に上げる 大東流合気柔術
この記事はブロとものみ閲覧できます

- 関連記事
-
-
 其の百五十八、はさむ 大東流合気柔術 東京稽古会
2017/10/24
其の百五十八、はさむ 大東流合気柔術 東京稽古会
2017/10/24
-
 其の百五十一、小指丘にかける 大東流合気柔術 東京稽古会
2017/08/08
其の百五十一、小指丘にかける 大東流合気柔術 東京稽古会
2017/08/08
-
 其の百四十六、剣を使う 大東流合気柔術
2017/06/15
其の百四十六、剣を使う 大東流合気柔術
2017/06/15
-
 其の百四十四、中心に上げる 大東流合気柔術
2017/05/22
其の百四十四、中心に上げる 大東流合気柔術
2017/05/22
-
 其の百四十二、捕らせる
2017/04/20
其の百四十二、捕らせる
2017/04/20
-
 其の百三十八、片手捕小手返
2017/02/19
其の百三十八、片手捕小手返
2017/02/19
-
 其の百三十三、小手詰
2016/12/24
其の百三十三、小手詰
2016/12/24
-
スポンサーサイト
tb: -- cm: --
| h o m e |


